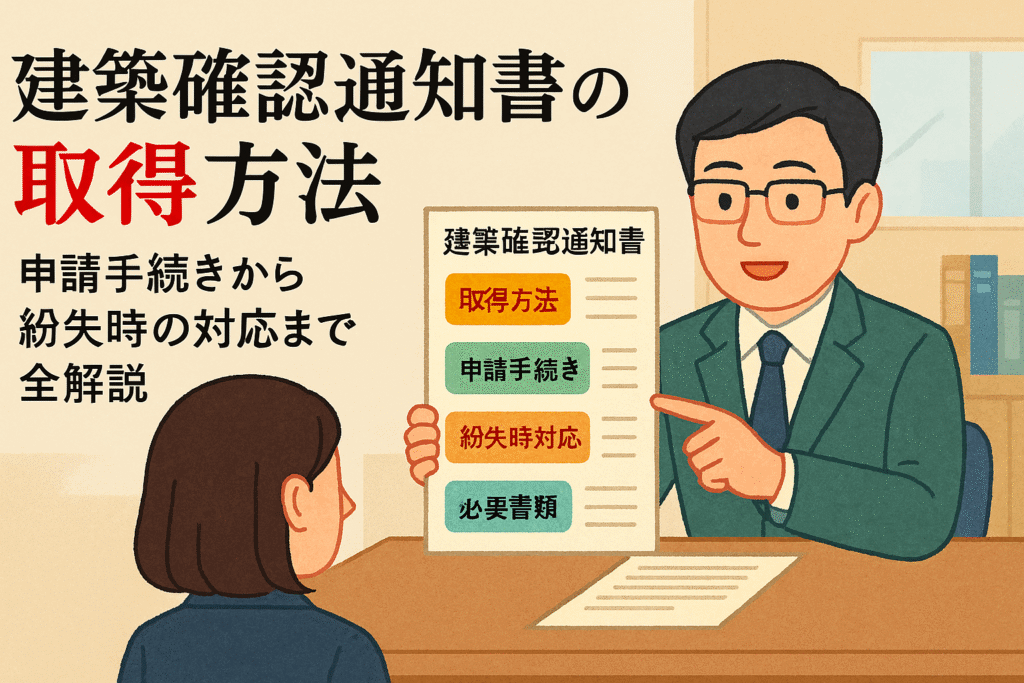「建築確認通知書って、どんな時に必要で、もし紛失したらどんなリスクがあるの?」――そんな疑問や不安はありませんか。建築基準法にもとづき規定される建築確認通知書は、全国で毎年【約40万件】以上の新築・増改築の現場で発行されています。不動産売却や住宅ローン審査、リフォーム工事まで、あらゆる建築・取引の現場で「正しい証明書類の有無」が大きなトラブル回避に直結します。
特に2025年4月の法改正以降、「省エネ基準への適合」や申請対象の拡大、書類保管ルールの変更など最新の制度対応が求められ、自治体ごとに運用も異なるため情報のキャッチアップが欠かせません。万が一紛失すると再発行手続きや取引遅延、余分なコスト発生など〈大きな損失リスク〉へ直結してしまうのが現実です。
「具体的な申請方法を知りたい」「どの書類が必要か整理したい」「もし手元にない場合はどうするの?」――このページでは、初めての方にもわかりやすく建築確認通知書の基礎知識から取得方法、2025年最新ルール、発行タイミングまで【実務で役立つポイント】を徹底解説します。
少しでもモヤモヤや不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。本記事を読むだけで、「いま自分が何をすればいいか」具体的な道標が手に入ります。
建築確認通知書とは?基礎知識と関連書類の違いを詳細解説
建築確認通知書の定義と法的意義―建築基準法に基づく役割と位置づけをわかりやすく説明
建築確認通知書は、建築基準法により定められた特に重要な書類です。敷地や建築物が法律や条例に適合しているか公的機関が審査し、その基準を満たしている場合に交付されます。新築・増築・改築・用途変更などを行う際に申請が義務付けられている建築確認申請に対し、審査が終わると交付されるのが建築確認通知書です。この書類は建築計画が法令に適合していることの公式な証明となり、これを受け取って初めて工事に着手できます。申請先は市役所や特定行政庁、または指定確認検査機関となります。個人住宅だけでなく、マンションやアパートなど大規模建築物にも同様の手続きを要します。
建築確認済証・検査済証・省エネ適合判定通知書との違いを整理
建築確認通知書のほかに、よく混同されやすい書類として建築確認済証、検査済証、省エネ適合判定通知書があります。それぞれの役割は下記の通りです。
| 書類名 | 主な役割 | 取得タイミング | 交付機関 |
|---|---|---|---|
| 建築確認通知書 | 計画が法令適合か証明 | 建築確認後(工事着工前) | 行政または検査機関 |
| 建築確認済証 | 通知書とほぼ同意 | 同上(同時交付が多い) | 同上 |
| 検査済証 | 建物完成後、完了検査で適合を証明 | 工事完了時 | 同上 |
| 省エネ適合判定通知書 | 省エネルギー基準への適合を証明 | 建築確認に併せて判定 | 行政等 |
書類名や取得のタイミング、目的が異なるため、必要な場面で正しく区別することが重要です。それぞれ保管が義務付けられており、不動産の売却や住宅ローン申請時に必要となることもあるため、大切に管理してください。
建築確認通知書の重要性―建築プロセスや不動産取引での持つ意味と影響
建築確認通知書は単に工事を始める際の必須書類であるだけでなく、建物の権利や将来的な不動産取引にも大きな影響を与えます。
-
建築工事開始の法的条件となる
-
売却時や住宅ローン審査で提出を求められることがある
-
行政による違法建築の抑制・トラブル防止に寄与する
-
紛失や未取得の場合、再発行手続き・証明取得が必要
新築マンションや中古住宅の売買時、不動産会社や金融機関が提示を求めることが一般的です。不備や紛失時は再発行手続きが可能ですが、市役所や指定検査機関で手数料が発生する場合があります。建築確認通知書が手元にないと、売却や相続、住宅ローン手続きが大幅に遅れる恐れがあるため、しっかりと保管し必要なタイミングで速やかに提出できるように備えましょう。
建築確認通知書の取得方法と申請手続きの全解説
取得可能な窓口―市役所や指定確認検査機関それぞれの特徴と選び方
建築確認通知書は、主に市区町村の役所や指定確認検査機関で発行されています。どちらを選ぶ場合でも、手順や審査の基準は建築基準法に準拠していますが、窓口によって対応スピードや相談体制に違いがあります。
| 窓口 | 特徴 |
|---|---|
| 市区町村の窓口 | 住民との繋がりが強く、公共建築や規模の大きな建築物に詳しい。 |
| 指定確認検査機関 | 民間主体でスピーディーな対応。平日の夕方や土日も相談しやすい所もある。 |
建築場所(都市計画区域か否か)や建物の用途・規模により選択肢が変わるため、事前に確認することが重要です。賃貸マンションや戸建てなどは、事業主が指定検査機関を使うケースも多く、申請者や建築士のアドバイスを参考にして選ぶと安心です。
申請に必要な書類一覧と記載例―見本を用いて具体的に説明
建築確認通知書の発行には、複数の書類を提出する必要があります。主な書類と記載例を以下にまとめました。
| 必要書類 | 内容と記載ポイント |
|---|---|
| 建築確認申請書 | 建築物の所在地・建築主氏名・設計内容を正確に記載。 |
| 設計図面一式 | 配置図、平面図、立面図、断面図など。各階ごとの詳細も必要。 |
| 構造計算書・仕様書 | 構造計算の根拠や使用資材の詳細を示す資料(主に鉄骨造やRC造で必要)。 |
| 委任状(代理申請時のみ) | 設計事務所や施工会社が代理で申請する場合は必須。 |
| 都市計画法などの関係法規資料 | 地域や敷地によって追加資料が必要になる場合がある(例:防火区域証明など)。 |
記載時の注意は、誤字や図面サイズの不備、不動産登記簿の記載忘れなどがあります。不備があると再提出となり工事が遅れることがあるため、慎重に確認しましょう。
建築確認申請から通知書発行までの期間とプロセス―2025年の法改正による変更点を含む
申請から建築確認通知書の発行までの流れは、次の通りです。
- 必要書類の準備と提出
- 担当窓口で審査(書類点検・設計内容の適合確認)
- 内容に問題なければ審査終了後、通知書発行
- 通知書が手元に届いてから初めて建築工事が着工可能
2025年の法改正により、審査期間の短縮とオンライン申請制度の拡充が盛り込まれています。標準的な審査期間は、戸建住宅でおおよそ7日〜14日程度、マンションや商業施設など大規模な建物では2〜4週間かかることが一般的です。法改正によって手続き負担が軽減されつつあるため、最新の申請方法や必要書類の変化にも注意しましょう。
建築確認通知書に関する法改正と2025年4月からの最新ルール
建築物省エネ法の改正内容―省エネ基準適合義務化の概要と対象範囲
2025年4月から施行される建築物省エネ法の改正では、すべての新築住宅と非住宅建築物に対して省エネ基準への適合が義務化されます。この改正により、従来は2,000㎡未満の小規模建築物が適用外となっていた範囲も対象となり、これまで以上に幅広い建築物に省エネ対策が求められることとなりました。これに伴い建築確認通知書に記載される事項も変更されています。
改正ポイントを表にまとめると以下の通りです。
| 区分 | 従来 | 2025年4月以降 |
|---|---|---|
| 対象建築物 | 一定規模以上の新築等 | すべての新築・増改築(住宅・非住宅) |
| 省エネ基準適合 | 一部義務・一部努力義務 | 全面義務化 |
| 建築確認通知書 | 省エネ仕様の記載は一部対象のみ | 全新築等に要記載 |
これにより、不動産売却や住宅の購入時だけでなく、新規建築・大規模リフォームを行うすべての建築物で新省エネ基準適合が証明される建築確認通知書の意義が高まります。
「新2号建築物」「新3号建築物」とは何か―用語定義と申請対象範囲の違い
2025年の法改正に伴い、「新2号建築物」「新3号建築物」という新たな区分が導入されました。それぞれの用語と申請対象範囲の違いを正確に理解しておくことが重要です。
-
新2号建築物:主に住宅や小規模事務所などで、特定の用途や規模の条件を満たす建築物が該当します。
-
新3号建築物:新2号建築物以外の中小規模の建築物が主な対象で、業務用施設やマンションの共用部等が含まれます。
両者の違いを比較すると下記のとおりです。
| 分類 | 主な用途例 | 適合義務 | 検査・確認手続き内容 |
|---|---|---|---|
| 新2号建築物 | 一戸建て住宅等 | 完全義務化 | 建築確認通知書・省エネ基準適合 |
| 新3号建築物 | 小規模オフィス等 | 完全義務化 | 建築確認通知書・省エネ基準適合 |
この新分類は、建築確認申請時に必要な書類や申請先にも影響を与えるため、用途や規模ごとに事前の確認が肝心です。
4号特例の見直しとリフォーム時の建築確認申請義務の拡大―実務者向けの法令改正ポイント
従来は小規模木造住宅に適用されていた「4号特例」についても2025年4月を境に大きな変更があります。これまで確認審査が一部省略されていた小規模建築物も、リフォームや増築の際は建築確認申請が必要となりました。これにより工務店や設計者、不動産所有者は省エネ基準の適合も含めて建築確認通知書を適切に取得・管理する必要があります。
主な改正ポイントは以下の通りです。
-
小規模住宅・木造でも大規模なリフォームは建築確認が必要
-
省エネ基準適合義務化にあわせて書類の提出・審査工程が厳格化
-
建築確認通知書の再発行・閲覧も厳密な手続きが設定
この結果、住宅売却時やマンション管理時にも建築確認通知書の保存・確認済証との違い理解が必須となります。書類紛失時の再発行には自治体窓口や市役所への正式な申請が必要なため、保管体制を事前に整えることが重要です。
建築確認通知書の記載項目と見本の徹底紹介
通知書のフォーマット―具体例を画像つきで解説(設計図面との連携説明)
建築確認通知書は、建物の新築や増改築などを行う際に法的適合を証明する重要な書類です。そのフォーマットは各自治体や審査機関によって若干異なりますが、主要な記載項目は共通しています。代表的なレイアウトは以下の表を参考にしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確認番号 | 個別の建築計画ごとに発行される番号 |
| 発行日 | 通知書が発行された日付 |
| 建築主の氏名・住所 | 建築主(施主)の氏名および住所 |
| 建設地 | 建物や施設の具体的な所在地 |
| 建築物の用途 | 住宅・店舗・工場などその他種類 |
| 階数・延床面積 | 建物規模を示す構造・階数・床面積など |
| 設計者/工事監理者氏名 | 設計図面や工事管理に関わる担当者の情報 |
| 確認済証の有無 | 確認済証とのセット発行の可否 |
| 備考 | その他特記事項 |
通知書は設計図面と連携し、建築物が建築基準法に適合していることを示します。審査機関による押印や電子発行への移行も増えています。内容に不明点がある場合、設計図面と照合して確認することが大切です。
各記載内容の意味と注意点―申請時のチェックポイント、誤記修正例も収録
建築確認通知書の記載事項にはそれぞれ明確な意味があり、確認の際は下記ポイントに注意してください。
-
確認番号: 申請時や各種手続きで求められるため、正確に控えておく必要があります。
-
建設地・建築主情報: 登記や売買時などに間違いがあると手続きが進まないため、内容を一字一句確認しましょう。
-
設計図面との整合性: 延床面積や用途などは設計図面と通知書で完全一致が求められます。差異があった場合は即時訂正が必要です。
-
訂正や修正例: 例えば建設地表記の脱字・誤字などは申請者自身で訂正届を提出し、審査機関の確認印をもらうことで最新状態にできます。
-
確認済証との違い: 建築確認通知書は手続きを進める上での承認証明、一方で確認済証は現地での工事開始時点で必要になる法的根拠となる書類です。
このように申請内容や記載事項に不備がないかを必ず確認し、万が一紛失した場合には早めに再発行手続きを進めてください。
省エネ適合判定通知書との併記時の取り扱い事例
省エネ基準への適合が義務付けられる新築や大規模な建築計画では、建築確認通知書と省エネ適合判定通知書が併記・発行されるケースがあります。具体的には、以下のような事例が想定されます。
-
一体型通知書発行: 省エネ適合判定が必要な場合、同時に建築確認通知書が発行されます。通知書内に「省エネ判定済」の欄が追加されている場合があります。
-
番号や発行日の分離管理: 両通知書が個別に発行される場合、発行番号・日付が異なるため、管理時は一覧表やクリアフォルダーで分けて保管します。
-
申請・提出のフロー: 建築主や不動産売却時に、両方の通知書提示を求められるケースも多く、併記が必要な場合は全書類をまとめて提出するのが基本です。
実際には、省エネ性能が建物評価や住宅ローン、売却時の価値にも影響するため、必ず適切に管理し、説明できるようにすることが重要です。
建築確認通知書が発行されるタイミングと受け取りの実務フロー
建築確認通知書はいつもらえるのか―申請から工事着手までの流れを最新事情とともに解説
建築確認通知書は、建築確認申請後に所管行政庁や指定確認検査機関によって発行されます。申請書類一式が建築基準法に適合しているか厳しくチェックされた後、合格すれば数日から1~2週間程度で準備されます。通知書の交付時期は、確認済証の発行と同時、または直後が一般的ですが、自治体ごとに運用差があるため担当窓口への確認が安心です。工事着手は建築確認通知書および確認済証の受領後でなければ認められません。通知書の発行元や発行タイミングが気になる場合は、申請書提出先・発行機関に直接問い合わせることで、最新情報や手続きの流れが把握できます。
マンションや戸建て別の受け取り状況―ケースごとの実例紹介
マンションや戸建て住宅の場合、建築確認通知書は建築主や施主にではなく、多くは施工会社や不動産会社がまとめて受領し、完成引き渡し時に所有者へ必要書類一式と一緒に手渡す形が一般的です。購入物件によっては購入時点ですでに建築確認通知書が保管済みで、手元に渡らないケースもあります。売買やリフォーム、住宅ローン申請で書類提示が必要となった場合は、管理会社や売主、不動産仲介業者に相談するとスムーズです。特に分譲マンションでは個別住戸単位での原本保管や再発行の可否、必要書類の範囲など細かな取り扱いルールが異なるため、早めに確認することが大切です。
確認済証や検査済証とのタイミング比較と適切な書類管理法
建築確認通知書とともに発行されることが多いのが確認済証です。両者は同様のタイミングで交付され、確認済証は工事着工許可の証明として法的に重要視されます。さらに工事完了後には検査済証が発行され、これは建物が法令基準に適合している証として必須です。下のテーブルでは主な書類の発行時期や管理ポイントをまとめました。
| 書類名 | 受け取る時期 | 主な保管者 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 建築確認通知書 | 確認済証発行時 | 施工会社・施主 | 申請内容が法的基準に適合した証明 |
| 建築確認済証 | 工事着工前 | 施主・施工会社 | 正式な着工許可の証明書 |
| 検査済証 | 工事完了時 | 施主・管理会社等 | 建物完成時の法令適合証明、資産価値や売却にも必須 |
書類は不動産売却や融資、リフォーム時にも活用されます。紛失時は発行機関に速やかに相談し、再交付や写しの取得など早めの対策をとることが望ましいです。書類管理を徹底し、安全・安心の資産運用を心がけましょう。
建築確認通知書の紛失時の対応と再発行手続き
紛失した場合のリスクと不利益―売買や登記におけるトラブル回避の重要性
建築確認通知書は、建築基準法に基づき建物の新築や増改築などの際に発行される重要な書類です。特にマンションや戸建ての売却、不動産登記、住宅ローン審査の場面では、この通知書の提出を求められることが多く、紛失による影響は大きいです。
主なリスクや不利益は以下の通りです。
-
不動産売却時、購入希望者や仲介業者に提出を求められる
-
登記手続きや住宅ローン申請時に審査で不利になる
-
市役所等に建築物の適法性を証明できない場合、追加の証明や対応が発生する
建築確認通知書がないことで契約や登記が遅れる、交渉が難航するなど大きなトラブルにつながるため、慎重な管理が必要です。
再発行の申請方法と必要書類―行政手続きの流れと費用目安
建築確認通知書を紛失した場合、再発行を申請できますが、行政機関への手続きにはいくつかのポイントがあります。
申請の流れと必要事項を以下にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 建築確認を受けた自治体の建築指導課・都市計画課など |
| 必要書類 | 申請書、本人確認書類、建設地や建築主の情報 |
| 手数料 | 通常数百円から数千円。自治体によって異なる |
| 発行までの時間 | 1日~1週間程度。状況や窓口の混雑度により異なる |
| 申請者 | 原則建築主。不明の場合は現所有者または代理人(委任状要) |
建築確認済証や検査済証も再発行の対象となるので、必要に応じて同時に申請すると効率的です。再発行申請の詳細については、各自治体のホームページや窓口での確認をおすすめします。
代替手段や書類調査方法―建築主や施工会社への問い合わせのポイント
建築確認通知書が手元になく、再発行も難しい場合は他の手段や調査方法も役立ちます。
- 建築主・前所有者への連絡
引渡し時に保管されていれば、建築主や前所有者、不動産会社に確認しましょう。
- 施工会社への問い合わせ
原本や控えを保管している場合があります。特に大手施工会社や分譲マンションの場合は記録が残っていることが多いです。
- 自治体での閲覧・情報開示請求
建築計画概要書や確認済証の閲覧・写し交付サービスを利用できる場合があります。
- 関連書類の有無確認
登記簿や検査済証、建築確認済証を探し、必要性に応じて補足資料として活用します。
建築物や所在地ごとに対応が異なるため、早めに必要書類や情報の有無を確認し、適切な窓口へ相談することが重要です。
建築確認通知書が求められる主なシーンと実務上の注意点
不動産売買時の書類提出義務とトラブル事例
不動産売買の際は、建築確認通知書の提出が必要となるケースが多く、売主と買主双方の信頼関係を構築する重要な書類です。建築基準法に適合した建築であることの証明として、買主や金融機関からの提出依頼を受ける場面が増えています。特に中古マンションや戸建住宅の売却時、建築確認通知書がない場合、取引が遅延するだけでなく、契約の解除につながることもあるため注意が必要です。
主なトラブル例を下記にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書類紛失 | 売主が建築確認通知書を保管していないケース |
| 建築確認済証との混同 | 建築確認通知書と建築確認済証の違いが分からず提出ミスが発生 |
| 手続きの遅延 | 必要書類が揃わず所有権移転やローン審査が進まず時間がかかるケース |
このような事態を防ぐため、事前に建築確認通知書の所在確認と保管を徹底しましょう。紛失時は速やかに役所や建築会社に再発行の可否を問い合わせることが肝心です。
相続や贈与の場面での利用法―名義変更と手続きの実例
不動産の相続や贈与の際にも建築確認通知書は大切な役割を果たします。名義変更の手続きでは、建物が適法に建築されている証拠として提出を求められます。特に古い不動産や増改築を経た物件の場合、書類不備により手続きがスムーズに進まない事例が多く見受けられます。
利用シーンとしては、以下のような流れになります。
-
法務局での名義変更申請時に提出が必要
-
登録免許税の減免申請時の証明書類として活用
-
融資や資産評価資料の根拠書類として提出
相続や贈与の手続きをスムーズに進めるためにも、不動産登記情報とあわせて建築確認通知書の有無や内容を早期に確認し、必要なら再発行も検討しましょう。
住宅ローン申請やリフォーム工事時に必要なケース
住宅ローンの申請やリフォーム工事を行う際にも建築確認通知書が重要です。金融機関は融資審査時、物件が違反建築でないかを確認するため、建築確認通知書や建築確認済証の提出を求めることが一般的です。特に新築や大規模リフォームの場合、確認通知書がないと融資が承認されない場合もあります。
また、リフォームでは増改築の確認申請や完了検査の一環として、建築確認通知書や検査済証の写しを求められることも多いです。書類が揃っていない場合、リフォーム計画そのものが立ち行かなくなることもあるため、細心の注意を払い、事前に関係書類を確認・保管しておきましょう。
建築確認通知書は紛失や未取得の場合、自治体や所轄の建築指導課に問い合わせることで再発行や写しの取得申請が可能な場合があります。住宅ローンやリフォームを検討する場合は、求められる書類の内容と発行手続きについて理解し、準備を怠らないことが安心かつスムーズな取引のカギとなります。
建築確認通知書を含む建築書類の整理・保管・デジタル活用術
書類紛失予防の保管方法と管理のベストプラクティス
建築確認通知書は、建物の法的適合性や後の不動産取引時、各種手続きで必要となるため、厳重な保管が重要です。まず原本の保管場所は火災や水害に備えた耐火・防水の書類ケースや専用ファイルを使い、湿気の少ない場所を選びましょう。書類の紛失や破損を防ぐため、住宅ローンや売却時にまとめて管理することで重要書類の所在が明確になります。実際の現場では、下記の方法が推奨されます。
-
強度の高いファイリングシステムに「建築」「確認済証」「検査済証」など書類ごとにインデックスを付けて管理
-
発行した日や建築基準法の改正日など履歴を記録しておく
-
万が一紛失した場合、発行元(建築主事・役所)での再発行申請方法を家族全員で共有しておく
小さな工夫が大きなトラブルの予防となります。
電子保存やバックアップの導入事例とおすすめツール
近年では紙の建築確認通知書をスキャンして電子保存するケースが増えています。パソコンやクラウドストレージを活用することで紛失や劣化リスクを低減できます。具体的には、以下のツールと手順がおすすめです。
| ツール | 主な特徴 | 推奨活用法 |
|---|---|---|
| Googleドライブ | 無料で大容量、PCとスマホ両方からアクセス可能 | 書類スキャン画像やPDFをカテゴリ分けで保存 |
| Dropbox | フォルダ同期や共有が簡便 | 家族や関係者と書類情報を安全に共有 |
| スキャナーアプリ | スマホだけで書類を高速データ化 | 外出先や急ぎの時もデータ化可能 |
スキャン時には「発行日・書類名・建物住所」などをファイル名に付け整理。さらに、USBメモリや外付けHDDへの2重バックアップも推奨されます。万一の端末故障や災害にも対応しやすくなり安心です。
建築履歴としての活用メリットと将来の不動産取引への対応
建築確認通知書は、建物の履歴情報として極めて重要な役割を持ちます。マンションや戸建て、または売却を検討する不動産でも「建築確認済証」「検査済証」とあわせて提示できると、買主や金融機関からの信頼が格段に高まります。
-
売却時に必要書類として提示を求められるケースが多い
-
建物の増改築・リフォーム時、確認申請や行政手続きで履歴証明になる
-
紛失している場合、再発行に時間がかかり取引タイミングを逃す恐れもあり
不動産取引や将来の物件管理効率を考え、住宅や所有建物の建築履歴は漏れなく管理しましょう。書類管理体制を整えておくことで、大切な財産をしっかり守ることにつながります。
よくある質問に対応したQ&Aセクション
建築確認通知書取得のよくある疑問解消
建築確認通知書は、建築物の新築・増築・改築・移転などを行う際、建築基準法に適合していることを証明する重要な書類です。不動産の売却時やマンション購入時にも求められるため、しっかり入手しておくことが大切です。通知書は通常、建築主が建築確認申請を行った後、所管の市役所や区役所の建築指導課などから交付されます。
通知書の取得場所は自治体によって異なりますが、以下が主な窓口となります。
| 取得場所 | 主な担当 |
|---|---|
| 市役所・区役所 | 建築指導課、建築審査課 |
| 指定確認検査機関 | 建築主が直接申請した場合 |
| 建築士事務所・施工会社 | 代理で手続きを行った場合、そこを経由して受領 |
申請後、建築計画が法令に適合していると認められると、通常1~2週間程度で発行されます。受け取った通知書は大切に保管し、住宅ローン手続きや売買契約時に提出できるようにしておきましょう。
建築確認済証や検査済証との混同を正すFAQ
建築確認通知書、建築確認済証、検査済証は似ていますが、それぞれ役割が違います。混同しやすいため、違いを明確に整理します。
| 書類名 | 発行時期 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 建築確認通知書 | 建築工事の着工前 | 建築計画の法適合を証明し、工事開始前の必須書類 |
| 建築確認済証 | 建築確認申請の許可時 | 建築確認申請が受理・許可された時に発行、通知書と併せて交付されることが多い |
| 検査済証 | 工事完了後 | 工事が建築基準法や設計通りに実施されたことを示す検査を通過した際に発行される最終書類 |
これらの書類は、それぞれのタイミングや提出先で必要になります。特に不動産の売却や金融機関での住宅ローン審査時は、全て揃っているか事前に確認しておくと安心です。
紛失時の手続きや発行タイミングに関する具体的な質問回答
建築確認通知書を紛失した場合も再発行が可能です。発行元である市役所や指定確認検査機関に申請し、本人確認書類や建物の所在地・台帳番号などが必要となります。再発行には数日~1週間程度かかることがあります。申請できる人は基本的に建築主や所有者に限られますので、ご注意ください。
発行タイミングについて、建築確認申請が承認されると、速やかに建築確認通知書が交付されます。申請後、工事開始までにこの書類が必要です。また、建築確認済証や検査済証の発行タイミングはそれぞれ着工前・完工後と異なります。書類の管理を怠ると後で手続きが煩雑になるため、しっかりファイリングしましょう。
【建築確認通知書の取得・再発行の主な流れ】
- 発行元にお問い合わせ
- 必要書類を準備
- 申請手続き(窓口または郵送)
- 再発行を受領
通知書が無い場合、建物の売却や住宅ローン申し込み、リフォーム時などで手続きが遅れる可能性があるため、なるべく早めに再発行を依頼することをおすすめします。